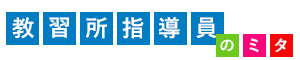大型自動車とは?
自動車はその大きさによって、道路交通法による区分がなされています。
いわゆる「トラック」と呼ばれることが多い大型自動車は、自動車の中では最も大きい区分となります。
大型自動車の定義としては、車両総量が11,000kg、つまり11トン以上で、最大積載量が6,5000kg以上となっています。
そして、乗車定員が30人以上のものについても大型自動車として分類されます。
これら3つの条件のうち、1つでも該当するものがあれば大型自動車とみなされるわけです。
当然、このクラスの自動車を運転するためには大型免許がないといけません。
普通車と比べるとその大きさの違いはかなりのもので、大型自動車は最大全長が12m未満となっていますので、車両感覚にかなりの差が出ます。
自動車免許の中でも最もハードルが高い免許と呼ばれるのも、こうした難しさがあるからです。
さらに大型自動車は普通自動車と比べると高さもあり、全高で3mを優に超えるため、場所によっては通れないところも出てきます。
運転席から見る景色も違ってきて、慣れが必要となります。
中型自動車とは?
大型自動車の下の区分となるのが中型自動車です。
その要件としては、車両総重量が7,500kg以上11,000未満、最大積載量が4,500kg以上6,500kg未満、乗車定員が11人以上29人以下となっています。
これらの条件を満たすものであれば、すべて中型自動車に区分され免許が必要となります。
日本国内においては、道路の幅や橋の重量制限などがあって大型自動車では通行できない区間が多く見られます。
その点で、荷物を運搬するのにどこでも走れるのが中型自動車となります。
こうしたことから運送業界では中型自動車のニーズが非常に高く、中型免許を持っていればさまざまなシーンで活躍できるようになります。
教習所にも、大型を取る前のステップとして中型免許を取る方がたくさんいます。
職員の方がよりサービスを拡大するために免許取得するケースも見られ、人気がある区分と言えるでしょう。
全長は8m弱となりますので、大型自動車と比べるとかなり運転は楽になります。
準中型自動車とは?
準中型自動車とは、車両総重量が7,500kg未満、最大積載量が4,500kg未満、乗車定員が10人以下の自動車です。
中型よりも少し小さめで、主に都市部で配送をする目的で利用されています。
大型免許などは年齢制限が厳しいですが、準中型免許だと18歳から取得できますので、より多くの人がチャレンジできるのが特徴です。
また、工事用車両でもこのクラスの自動車が多く見られますので、建設業界の方でも取得しておくと運転できる車両の範囲が広くなります。
普通自動車よりもちょっと大きいくらいの感覚ですので、運転しやすい区分と言えるでしょう。